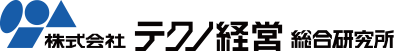工業的に生産された初めての無機繊維であるグラスファイバー。強度や耐熱性、不燃性、電気絶縁性、耐薬品性といった特徴を持ち、広範囲の産業で利用されている素材だ。さらに、このグラスファイバーを樹脂と合わせることで、FRP(繊維強化プラスチック)やFRTP(繊維強化熱可塑性プラスチック)といった新たな素材へと生まれ変わる。このように強化されたプラスチックは複合材料として、自動車の部材をはじめ、スマートフォンの筐体やバスタブなど、日常生活のあらゆる場面で活用されている。
1923年(大正12年)、福島県で繊維メーカーとして創立された日東紡績株式会社。「何でも繊維にしてみよう」というモットーのもと、1938年(昭和13年)に世界で初めてグラスファイバーの工業化に成功するなど、新たな技術を生み出し、これまでに存在しない世界初、日本初となる素材を創出してきた。多種多様な分野にも事業を拡大し、ヤギの血清由来の抗体を用いた体外診断用医薬品や、独自性の高い機能性ポリマーを開発するなど、時代のニーズに合った製品を生み出し、社会課題の解決への貢献を続けている。
2023年(令和5年)に創立100周年を迎え、次の100年に向けた新たな挑戦が始まる中、開発から製造、販売までを一体化させた組織運営と顧客視点の強化をめざして、これまでの3事業部門制から5事業本部制へと組織体制を変更。厳しいビジネス環境下で、いかにして安定した基盤を創り、次代の人材育成をめざすのか。新体制の一角を担う複合材事業本部で新たに導入された加工工程の改善プロジェクト、さらにはビジネス戦略のコンサルティングまで発展した複合材事業改革「fBIT活動」について、執行役 複合材事業本部長 伊藤 正毅 様、副本部長 兼 富士ファイバーグラス(株) 代表取締役社長 永田 広一 様ならびに活動メンバーの皆様からお話を伺った。
(※ASAP 2025年 No.1より)
日東紡の基幹ビジネスとして発展したガラス繊維事業
会社の概要等についてお聞かせください
伊藤 正毅氏:
日東紡績株式会社は今年で102年目、100年企業の一つということで歴史のある会社です。もともとは日本の基幹産業であった繊維、この繊維からスタートしたのですが、その繊維をガラスの繊維に変えて、現在はそれを基幹ビジネスとして、ここ2年ぐらいは非常に良い収益を上げています。
我々複合材事業本部では、主にプラスチック強化材としてのガラス繊維を製造・販売しており、グループ従業員2,690名(2024年3月31日現在)のうち約500名が当該事業に従事しています。

執行役
複合材事業本部長
伊藤 正毅 氏
永田氏: 複合材事業本部は、グラスファイバー、いわゆるガラスでできた糸をもとに、その細い糸を束ねたり、短くカットしたり、あるいはすりつぶして粉のようにするなど、用途に合わせてさまざまな形状のものを製造しています。これらの素材は、例えばユニットバスや自動車のパーツなど、プラスチックに見えるものの中に複合材として混ざっていて、直接目に触れることはありませんが、世の中の役に立つべく、製造・販売している事業部となります。

副本部長 兼
富士ファイバーグラス(株)
代表取締役社長
永田 広一 氏
永田氏: 日東紡績株式会社の子会社にあたります。栃木県真岡市にあり、58年の歴史がある会社です。主に複合材という最終商品になる元の原繊、グラスファイバーを製造しており、同事業部で福島県福島市郷野目にある福島事業センターとともに、お客様に対しては日東紡の商品という形で、同じ品質、同じ性能で提供できるものづくりを行っています。
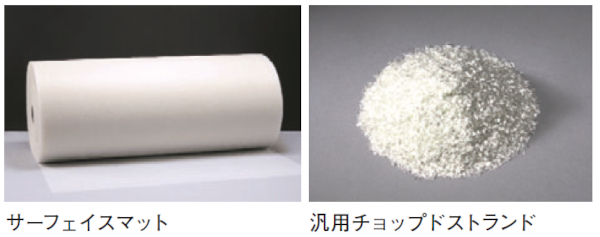
業界をリードする新しいガラスの開発
品質安定性、供給安定性も強みに
貴社ならではの強みについてお聞かせください
伊藤 正毅氏:
パパっと撒いた時に平らになる、平滑性のあるガラスといった特殊なもの、こうした新しいガラスの開発は他のガラスメーカーに先駆けて、日東紡が業界をリードしてきました。そこが強みですね。ただ、こういった時代ですので、追従する競合他社というのも多く、時を置くと同じような性能のものが出てきます。そこは、その先をいく、オンリーワンを創るという進取の気性といいますか、新たなものに挑戦していく、非常に高い志を持っています。
あとは、もし我々がリードしていた素材が真似をされるようになったとしても、やはりお客様側から見れば、品質にばらつきがない、同じ物性のものが安定的に出てくるなど、要するに品質安定性と供給安定性といった部分でご評価いただいているかと思います。非常に厳しい環境ではありますが、こうしたお客様のご期待に応えるべく、しっかりと取り組んでいかなければならないと感じています。
価格競争やコスト上昇など、厳しい
環境下だからこそ、将来への改革を
事業環境についてお聞かせください
伊藤 正毅氏:
売上に関しては、決して近年落ちているわけではないのですが、残る利益は少なくなってきています。それはやはり、製造上のコスト上昇という部分でどうしても抗えないといいますか、エネルギーをはじめ、さまざまな物価、原料費、もちろん人件費も。これらのカーブだけは、なかなか右下がりにはできない。ガラスをもとにさまざま素材や製品を作り出すという、コストのかかるプロセスを持っている以上、我々はそこを上がらないように工夫はするのですが、どうしても上昇基調ではあります。一方、販売量は落ちていませんが、競争の上でお客様にご購入いただくため、販売価格についてはある程度の競争レベルに持っていかなければなりません。
このような状況下で我々の事業本部は、販売面では競合が増え、価格競争の世界にきており、製造面のコストは右上がり基調ということで、非常に厳しい環境だと考えています。現状のままではいけないという危機感のもと、思い切った改革を仕掛けていこう、というところです。
複数の加工工程に潜む改善ポイント
クローズ型の環境も課題に
弊社のコンサルティングを導入する前に、どのような課題をお持ちだったのでしょうか
永田氏:
富士ファイバーグラス株式会社は加工工程が複数あり、ラインが異なります。そのため、それぞれに改善ポイントや悩みがあるという状況でした。どこの企業様でも同様かと思いますが、課題はたくさんあるものの、例えば人が足りないなど、私自身の熱い思いがあってもリソースが無い。そのため、外部のプロにお尻を叩いてもらいながら、力量のバランスも取りながら手綱を引いてもらって成果を出し、そしてその成果が働くみんなの成功体験になって、さらにスキルアップしていきたいという想いを持っていました。
日東紡績株式会社は、グローバル・ニッチNo.1を創造し続ける企業グループとして、グラスファイバーにおいて世界一を誇る、さまざまな技術を保有しています。一方で、言葉を悪くすれば保守的で、あまり外部との技術交流がなく、クローズ型で社内展開が多い。そのため、いわゆるガラパゴス化してしまうような瞬間もあり、実はグラスファイバーを作る以外の部分では、他の企業様は自動化や平準化など、どんどん進化している状況です。それがここ5年、10年程で気づきはじめ、視野を広く持つ人材が増えたことによって、ようやく外部の力というところにも、きっちり目が向くようになったと感じています。
1日の短時間で課題を見抜く工場診断
製造現場への指導力が決め手に
弊社の1日工場診断を受けた印象はいかがでしたか
永田氏: ご指摘いただいた内容は、はっとするものばかりでした。例えば、ラインの中で監視という項目があります。現場のメンバーは「品質ルールがあるので、2名は欲しい」と主張しましたが、実際には用事かなにかで1名が監視を外れることもあり、そうであれば1名でよいのでは、とご意見をいただきました。全くもってその通りで、こういった細部まで1日の短時間というスピード感でさっと見抜く、さすがプロだなと。今でも、このやり取りは印象に残っています。
伊藤 正毅氏: 私は直接、工場診断の現場を見ていないのですが、それに関わるお話をいただいた時、現場の「見える化」が上手だなと感じました。工場内にさまざまな設備があり、そこに作業者が何名いるかというのをマッピングしていく。そうすると、密な部分や手薄な部分、逆に抜けている部分など、こういったものが一目で分かります。コミュニケーションだけではイメージしづらいところが、すぐに理解できる。これがやはり工場診断でも、今の現実はこうだと、現状を把握して見えるようにするといった部分が、最初の取っ掛かりとしては非常に大事なのだなと思いました。
コンサルティング導入の決め手はありましたか
永田氏: もともとは省エネの改善活動でテクノ経営さんのコンサルティングを導入しており、すごく良い成果を上げていただいていました。現在でも、日東紡グループの中では、その活動が非常に評価されています。それを聞き、少し調べさせていただいたところ、現場改善などをはじめ、いろいろとお助けいただけそうだなと。和田さんは若くはつらつとした、すごく優秀な方が来てくださったという印象で、ご提案では私の望んでいる部分と非常に波長が合うといいますか、これはという形でお願いさせていただきました。
伊藤 正毅氏: 私は省エネの改善活動を導入する際、検討メンバーだったのですが、正直に申しまして、テクノ経営さんは現場を視察、診断して問題点をまとめ、それを提案するところまでは得意だけど、現場で実践的な指導をするのはそれほどなのでは?と思っていました。ところが、永田から現場での改善活動で、目に見えて成果が出ていると聞いて驚きました。よくある管理的なコンサルティングではなく、製造のプロセスを深く理解していて、しっかりフォローアップまで行っていただける。まさに今、我々に足りていない部分をカバーしてもらっています。現在は事業本部の戦略部分でもお手伝いいただいていますが、複合材というのは製造プロセスが分かっている方でないとダメなので、そこは非常に助かっており、本当に良かったなと思っています。
課題の未達成で意気消沈した導入当初
工程の改善に合わせて人材も成長
コンサルティングを導入した当初はいかがでしたか
永田氏:
今回導入の際に、実はもう一つ仕掛けたことがありまして。私がもともと所属していた日東グラスファイバー工業株式会社の人間を引っ張ってきて、加工課を任せました。富士ファイバーグラス株式会社では私と同じく、同じグループ会社ではありましたが外部からきた人間でした。
その彼が現場のベテランチームを牽引するわけですが、最初は現場のリーダーたちがやる気を削がれるだろうなと考えていました。案の定、月ごとの課題が達成できないなど、見事に落ち込んでしまい……。それも想定内でしたが、恐らく自社の中だけで実施していたら、多分そのままフェードアウトして改善チームがお開きになっていたと思います。ここがポイントで、まさに期待していたところでもありましたが、和田さんは落ち込む暇を与えないようなスピード感で対応し、きっちりと成果物を出していく。本当に苦労をお掛けしたと思いますが、何度も粘り強く指導いただき、工程の改善と合わせて、リーダーたちも少しずつ成長していきました。
現場の皆様はどのように感じていましたか
M.N.氏: ロービングの工程では1つの生産台を作業者1名で受け持ちますが、どうしても個人の能力によって差があるという点が課題でした。作業者の割り振りを現場のリーダーに任せていたので、一番初めに価値効率を考慮した人員配置を理解してもらうことが大変でした。

製造部加工課
ロービング係 係長
M.N. 氏
H.S.氏: マット工程の作業が慢性化していたため、問題点がどこか、どうすれば生産性が向上するのかが全く見えていなかったところが一番の課題でした。また、導入当初の段階ではデータの収集をはじめ、何がムダで、何が必要かというのを現場のみなさんに周知させるところが一番苦労しましたね。

製造部加工課
マット係 係長
H.S. 氏
K.S.氏: 活動当初、現場にヒアリングをしたところ、よくわからない暗黙のルールといったものがあり、そこを改善することから取り組みました。最初は抵抗があったものの、慣れてしまえば、なぜ今までこれを実施していなかったのかといった感じです。現在は設備を改造してどんどん生産性を良くしようといったフェーズに入っています。

製造部加工課
チョップ係 係長
K.S. 氏
Y.I.氏: ヤーン工程でも、これまで続けていたことでどこにムダが潜んでいるのか、私自身もわからない部分が多く、苦労しました。徐々に理解が進み、作業者に伝えるのですが、作業者自身もこれまでやってきたことをいきなりやらなくていいというのは、やはり抵抗がありました。

製造部加工課
ヤーン係 係長
Y.I. 氏
K.Y.氏: 活動当初、データの収集を始めましたが、作業者の方はデータ取りをやったことがなかったため、続けられるのかという不安がありました。その点は、データ記入用の用紙やフォーマットを用意することで対応いただくことができました。

製造部加工課
RCセンター 係長
K.Y. 氏
仕事に対する物事の組み立て方が変化
8名の少人化に加え、工程間の連携も
コンサルティング導入の成果をどのように感じていますか
永田氏:
各セクションのリーダーまで、物事のまとめ方が上手になったと実感しています。例えば、設定した歩留まりから良かった、悪かったという結果を考察し、それをもとに次月の対策案を練るなど、業務に対する組み立て方が自然と身についた印象です。
具体的な成果では、現状でのべ8名程度の少人化を実現しています。そもそも現場の人材が足りていない中、以前の想定よりも少ない人数で同じ生産ができるようになった、それが一番すごいなと思いました。また、現場の工程間で連携できるようになったことも大きな変化です。最終形態によってロービング、マット、チョップ、ヤーンという4つの工程があるのですが、同じ加工課に属しながらも、各工程間には見えない壁がずっとありました。それぞれの工程内ではプロフェッショナルでも、他工程のことは全く分からないなど、一緒に改善しようとしても上手くいかない。そこを平準化していくことで、他工程への応援が可能になり、人時生産性の改善はもちろん、現場の作業者も他工程の仕事を身につけ、幅がひろがりました。
I.I.氏: 富士ファイバーグラス株式会社は、ものすごく風土や風習、暗黙知、慣例といったものが混ざり合ったような工場になっていました。そこから脱却するために和田さんからいろいろとアイデアをいただきながら活動を進めて参りました。現場の各工程を担当しているリーダーから、前向きな意見が出てくるようになったというのは本当に感動しています。この活動がなければ実現しなかったことだと感じています。

製造部 次長 兼
製造部加工課 課長
I.I. 氏
新たなタスクフォースの立ち上げ
次代に向けたビジネス戦略をサポート
複合材事業本部における戦略会議でのコンサルティングにまで発展した経緯などをお聞かせください
伊藤 正毅氏:
現在の事業環境は非常に厳しく、また急に良くなることもありません。こうした世の中の大きな動きの中で、事業本部として5年後、10年後も継続的に活動していける基盤が必要です。どのような環境でも、ぶれない組織体制、構造、新たなビジネス、こういったものを今から創り上げていくために、タスクフォースを昨年11月に立ち上げました。その際、永田と相談し、ここにもコンサルティングに入ってもらおうと考えました。こうした活動は大抵が言いっ放しで終わるため、それではいけないと。しっかりとファシリテーションを行っていただける方が必要でした。
最初はブレーンストーミングから入るのですが、私と永田の性格から、話がどっかに行ってしまいがちで……。そういった点で和田さんは、ぎゅっと話を戻していただいて、さらにカテゴリーに分けたアクションや具体的に狙っていく数字を相談いただくなど、進行だけではなく、戦略をしっかりと前に進めてくれます。我々が一生懸命にアイデアを出し、どういう問題があるかに集中できるといいますか、非常にやりやすいですね。今後、実行フェーズに移っていきますが、予定通り進めば、現状で考えているレベルの収益改善までは達成できる道筋が見えています。
複合材事業本部が継続する基盤創りと
未来を担う人材の育成をめざして
今後の目標やめざす姿をお聞かせください
伊藤 正毅氏: タスクフォースのミッションは、5年後、10年後も事業が継続していることだと思っています。目標は非常に高く掲げていますが、毎年の収益がずっと安定している事業にしていきたい、そこが本当に期待している部分です。風土と組織、そして事業そのものもありますが、この改革を今、やっておく必要がある。一緒にやっているメンバーは30代、40代で、この人たちが10年後、20年後も複合材事業本部という場所で元気に仕事をしていて欲しいので、そのための基盤をどうやって創っていくか、ここに一番力を注いでいきたいですね。
永田氏: タスクフォースが実行フェーズに入ります。富士ファイバーグラス株式会社でも体験したように、この麹町の本社で営業、開発、管理といった人材が同じように、毎月の決めたことをしっかりとやり遂げる。その結果という部分はこれから見ていく必要がありますが、絶対達成します。その暁には、工場とはまた違ったフェーズで成功体験につながる。タスクフォースのメンバーは、次の日東紡績株式会社を背負う人材です。そのメンバーたちに成果を実感させたい。自分たちはこういったプログラムで、しっかり成果を上げたのだと。次の世代を育てていくことも目標にしながら、実行フェーズを楽しんでいきたいですね。

インタビュー風景
I.I.氏: 当初掲げた目標の達成というのは大前提で、そこから何をやっていくのかが今の活動における基盤となっています。和田さんのような優秀な方に指導いただいておりますので、有意義な活動にしたいというのは逐一思っていますし、これからは他工程の活動や複合材事業本部での戦略会議も進んでいますので、そういった連携を深めながら、さらに飛躍していきたいと考えています。
M.N.氏: いろいろな仕組みを改善し、日々の生産を100%に近い状態に持っていきたいですね。そのためには機械の稼働を止めない工夫が必要ですので、前工程の部門や設備課とも協力しながら進めていきたいです。
H.S.氏: 意識は変わりつつありますが、もっと高めていきたいですね。作業者一人ひとりが自分たちで考え、解決していけるようなところまで持っていければベストかな。他工程とのつながりも強化しつつ、協力して強くしていければというのが今の目標です。
K.S.氏: 少人化をめざし、他からフォローを入れつつ、2名を1名にできました。最初に大きな効果が出た部分ですが、フォローにまわるのは現場のリーダーなど、ベテランの作業者であることが多く、彼らの負担が大きくなっています。少しでも皆のレベルを上げて、負担をなくしていきたいと考えています。
Y.I.氏: 突き詰めれば、まだまだムダ作業というのは絶対に隠れていると思います。作業者のスキルアップはもちろん、一番の理想は自分でそういったムダに気づけることですので、そこの意識づけというのは今後も継続し、作業者自身がもっと生産性を高めていけるようにしたいです。
K.Y.氏: 作業者の方々の意識を高めてもらうことと、検査では自動化が進んでおり、他にもまだ省ける作業はあると思いますので、引き続き、活動を支えていきたいですね。
取材にご協力いただいた方
日東紡績株式会社
執行役 複合材事業本部長 伊藤 正毅 氏
副本部長 兼 富士ファイバーグラス(株)
代表取締役社長 永田 広一 氏
富士ファイバーグラス株式会社
製造部 次長 兼 製造部加工課 課長 I.I.氏
製造部 加工課 ロービング係 係長 M.N.氏
製造部 加工課 マット係 係長 H.S.氏
製造部 加工課 チョップ係 係長 K.S.氏
製造部 加工課 ヤーン係 係長 Y.I.氏
製造部 加工課 RCセンター 係長 K.Y.氏
PDFダウンロード
【コンサルティング事例】 日東紡績株式会社・富士ファイバーグラス株式会社 様